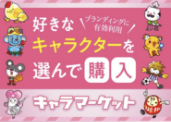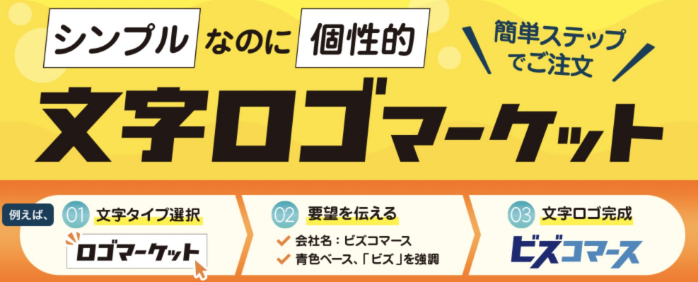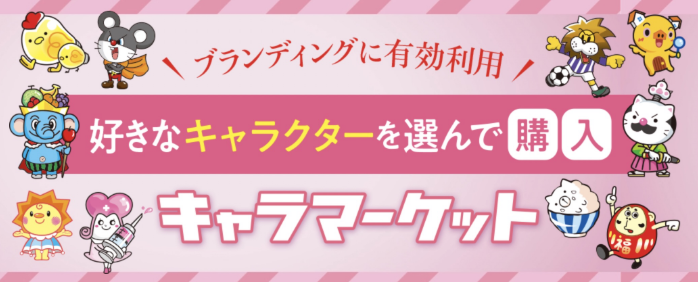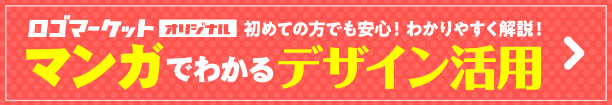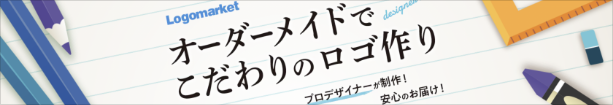Contents
相場は“誰に何まで頼むか”で変わる。目安は個人3〜15万円、制作会社10〜50万円、専門会社20〜30万円台が中心
ロゴ料金は一律ではありません。依頼先のタイプ(個人・制作会社・専門会社)、提案数や修正回数、権利やガイドラインの範囲、スケジュールの厳しさで上下します。公開情報を横断すると、個人・フリーランスで3〜15万円、制作会社で10〜50万円、ロゴ専門会社で20〜30万円台がボリュームゾーン。クラウドソーシングや格安プランでは数千円〜数万円の事例もありますが、納品形式・修正・権利の条件を事前に精査しないと、結局高くつくことがあります。
料金相場の全体像と、金額が変わる理由
ロゴの料金は一律ではありません。依頼先のタイプと、どこまでを作業範囲に含めるかで大きく変わります。まずは全体像を地図のように把握し、そのうえで自分の案件がどこに当てはまるかを見極めるのが近道です。下の表は、一般的に語られる目安レンジと、向いているケース・注意点を整理したものです(あくまで目安。実際は要件とスケジュールで上下します)。
依頼先別の料金相場(目安)
| 依頼先タイプ | 料金の目安 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| クラウドソーシング・格安系 | 数千円〜数万円 | とにかく安く早く、比較用のドラフトを見たい | 修正や権利、納品形式の条件差が大きい。最終的に追加費用になりやすい |
| 個人・フリーランス | 3〜15万円 | 直接対話しながら素早く形にしたい、小規模案件 | 守備範囲は人に依存。商標・ガイドラインなどは別途相談になりやすい |
| 制作会社・デザイン事務所 | 10〜50万円 | 複数案・分業・品質安定、展開物まで見据えたい | コストは上がる。社内合意や工程管理の分だけ期間も伸びる |
| ロゴ専門会社 | 20〜30万円台中心 | 運用ルールや並列表記まで含め、一気通貫で整えたい | 要件定義が精緻。関係者が多いほど打合せ回数が増えがち |
| 著名デザイナー・大規模刷新 | 50万円〜数百万円以上 | 企業再編や上場前後、海外展開など戦略と一体の刷新 | 期間・調整コストが高い。CI/VI全体設計とセットになることが多い |
上の表に自分の状況を当てはめ、次の「作業範囲」と「条件」を決めると、見積り比較が手早く公平になります。
よくある料金レンジの具体例(イメージ)
金額だけを眺めても判断しづらいので、費用帯ごとに含まれやすい作業のイメージを文章で押さえておきます。もちろん実際のプラン設計で増減します。
- 3〜5万円
初回提案1〜2案、修正は1〜2回、納品はPNG中心。AIやSVGは追加費用になりやすい。ドラフト検討や仮運用に向く。 - 5〜15万円
初回提案2〜3案、修正2〜3回、AI/SVG/PDF/PNGを一式、単色・反転・縦横ロックアップまで含む例が増える。小規模事業の実戦投入ライン。 - 15〜30万円
方向違いの提案、最小サイズ検証と暗背景テストの報告、簡易ガイド(サイズ・余白・色・並列表記)を含めやすい。web・紙・看板の多面運用を想定。 - 30万円以上
競合・市場の簡易調査、ネーミング接続やタグライン整理、商標の一次調査を含めたプランに発展。関係者が多い案件の合意形成にも向く。
価格が上下する主な理由
同じ「ロゴ制作」でも、入っている作業の幅と深さで費用は大きく動きます。見積書では次の観点を確認します。
- 初回提案の幅
何方向で、各方向何案を提示するか。方向が増えるほど調査・検討と制作時間が増えるため、費用は上がります。 - 修正回数と工程設計
無料で直せる回数と、超過時の単価。段階的レビュー(ラフ→清書→最終)を厚くするほど時間がかかります。 - ヒアリングと調査の厚み
事業理解、競合・市場の確認、使用シーンの棚卸しなどの前工程は、当たり外れを減らす保険でもあり、費用にも反映されます。 - 権利と商標の扱い
著作権を譲渡するのか、利用許諾なのか。商標は簡易確認か専門調査まで行うのか。範囲が広いほど費用は上がります。 - 納品データの範囲
AI・SVG・PDF・PNGの形式に加え、単色版・暗背景版、縦横ロックアップの有無。運用の“実戦力”をどこまで持たせるかで変動します。 - ガイドラインの有無
サイズと余白、色の使い方、暗背景、並列表記などをルールとしてまとめるか。作るほど再現性は上がり、費用も上がります。 - スケジュールと体制
特急対応、夜間・休日対応、打合せ回数、関係者の数。合意形成が難しいほど時間が必要です。 - 経験値とリスク対応
実績や専門性、トラブル時の一次対応、検証レポートの有無など。品質保証やリスクヘッジは費用に跳ね返ります。
見積りで気をつけたい“赤旗”と“安心材料”
赤旗になりやすいポイントは、総額だけで内訳が空白、提案数や修正の上限不明、納品がPNGのみ、権利が曖昧、無料提案の境界が不明、といった不透明さです。
安心材料は、提案数・修正範囲・納品形式・権利・商標・ガイドライン・追加費のトリガー・初回提案の目安日程が明記されていること。ここまで見えれば、複数社の見積りを公正に比較できます。
価格を抑えつつ質を落とさないコツ
最初に範囲を文章で固定してから相談すると、無駄な往復が減ります。たとえば「提案3方向×各1案、修正3回、AI/SVG/PNG、単色・反転・縦横ロックアップ、簡易ガイド4ページ、最小サイズと暗背景の検証を報告」といった具合に、必要最低限の“実戦力”をセットで指定します。さらに、案の方向を最初から分けて依頼すれば、追加提案の発生自体を抑えられます。権利と商標は段階的に、まず簡易確認から入るのが現実的です。
料金がどう決まるか(内訳の読み方)
見積書に頻出する項目を平易に言い換えると次の通りです。用語の切り分けが分かれば、比較が一気に楽になります。
- デザイン制作費:ロゴそのものの設計にかかる中核費。個人5〜15万円、制作会社10〜50万円が目安。
- 提案費(案数):初回で何方向・何案提示するか。追加は1案あたり1〜2万円が相場
- 修正費:無料の範囲と回数の上限、追加単価の明記を確認。
- 調査・ヒアリング:戦略整理、競合・商標の事前確認、使用シーンの棚卸しに充当。金額は開示幅が大きい。
- 権利関連:著作権の扱い(譲渡か利用許諾か)と商標調査の範囲。譲渡がプラン内の例もあれば、別費用5〜10万円とする例もあります。商標の一次調査は数万円規模が一般的。
- 納品データ:AI・SVG・PDF・PNGなどの形式と、単色・反転・ロックアップの有無を確認。
- ガイドライン:色・余白・最小サイズ・並列表記・暗背景版などの簡易ルール。上位プランや別建て計上が多い。
- スケジュール:初回提案の目安、特急対応の可否と加算。
見積書の“赤旗”と“グリーンフラッグ”
赤旗になりやすい例
・総額だけで内訳が白紙、提案数や修正回数の上限がない
・納品形式がPNGのみでAI/SVGが含まれない
・権利が不明確(著作権譲渡か利用許諾か、フォントや素材の商用条件)
・無料提案の条件が曖昧(採用時のみ有料などの境界が不明)
こうした不透明さは、後の追加費用や法務リスクに直結します。
グリーンフラッグ
・提案数、修正範囲、納品データ、権利、商標調査、ガイドラインの有無が明記
・追加費用のトリガー(修正超過、案追加、特急)が定義済み
・初回提案までの目安日程が提示されている
公開情報でも、こうした条件を明記する会社は安心材料が多い傾向です。
ケース別の現実解(費用配分の考え方)
小規模店舗の新規開業(まず看板・名刺・SNSが必要)
予算3〜10万円で、個人や小規模制作側のプランを軸に。初回2〜3案、修正2〜3回、AI/SVGと単色・反転を確保。商標は一次調査まで。
スタートアップのサービス立ち上げ(ウェブ・アプリ展開)
予算10〜30万円で制作会社または専門会社に。方向違いの提案、反転・単色・縦横ロックアップ、簡易ガイド、ラストで小サイズ検証の報告まで含める。
上場準備やリブランディング(全社展開・CI/VI)
予算50万円〜。ステークホルダー合意、ブランドアーキテクチャ整理、商標調査の専門委託、ガイドラインの章立てまで実装。
ここで差がつく三つの交渉術
範囲の固定化
最初に「提案3方向×各1案、修正3回、AI/SVG/PNG、単色・反転・縦横ロックアップ、簡易ガイド4ページ」を文章でセット化。曖昧さを減らすほど総額の予見性は高まります。
追加費の“地雷除去”
案追加はいくら、修正超過1回いくら、特急対応の条件は何か、を事前に明文化。公開例では1案あたり1〜2万円の加算が目安。
権利と商標の経路設計
著作権譲渡がプラン内か別費用か、商標は簡易調査か専門調査か。専門調査や出願費用は別途数万円以上が相場感です。
見積もりチェックリスト(コピペ可)
- 依頼目的と使う場所(名刺、看板、ウェブ、SNS、アプリ)
- 初回提案の方向と点数(例:幾何学/有機/モノグラムの3方向)
- 修正回数の上限と超過単価
- 納品データ(AI/SVG/PDF/PNG)と単色・反転・縦横ロックアップ
- 最小サイズ検証と暗背景テストの有無
- ガイドラインの範囲(サイズ・余白・色・並列ルール)
- 権利(著作権の扱い、フォント・素材の商用条件)
- 商標調査の範囲(簡易/専門)
- スケジュール(初回提案の目安、全体の里程標)
- 追加費の発生条件(案追加、修正超過、特急)
このチェックポイントは、各社の公開条件や相場記事の“よくある抜け”を踏まえた最低限の論点です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 3万円未満の見積りは危険?
A. 危険とは限りません。ただし、時間単価と作業範囲の現実性を確認しましょう。極端に安い場合は、修正や権利、データ形式が限定され、結果的に追加費用が重むこともあります。
Q2. なぜ同じ“ロゴ”なのに価格差が大きい?
A. スコープの違い(調査・戦略・案数・修正・権利・ガイド・運用支援)と、デザイナーやチームの経験値が主因です。制作会社と個人、専門会社では提供する“前後工程”が違います。
Q3. 追加提案の相場は?
A. 多くの公開例で1案につき1〜2万円が目安。最初に方向を分けた提案設計にしておくと、追加の必要が減ります。
Q4. 著作権は譲渡すべき?
A. 長期運用や二次展開を考えるなら、譲渡または広範な利用許諾が安心。譲渡をプラン内に含む例もありますが、別費用のケースもあるため事前確認を。
Q5. 商標はどこまでやるべき?いくらかかる?
A. 既存と衝突しないかの一次確認は必須。専門調査や出願は別途費用で、一次調査〜1区分の手続きまで含めたサービスで数万円規模の相場感も見られます。
Q6. 自作や無料ツールとの違いは?
A. PNGの仮ロゴは用意できても、拡大に耐えるSVG、運用ルール、並列表記対応など“実戦力”は不足しがち。印刷・看板前提なら有償化の判断が早いほど総コストを抑えられます。一般的相場記事でも、依頼先による範囲差が費用の本体だと示されています。
まとめ:相場より“条件”を見る。
相場の数字だけでは、適正価格は判断できません。損しないコツは、範囲を言語化すること。提案数や修正、納品形式、権利と商標、ガイドライン、スケジュールと追加費の条件まで先に文章で固定すれば、見積もりの比較は一気にフェアになります。全体感としては、個人3〜15万円、制作会社10〜50万円、専門会社20〜30万円台が中心帯。クラウドソーシングはドラフトや試用に最適ですが、採用時は権利と納品形式をクリアにしておきましょう。ここまで整えてから複数社に同条件で問い合わせれば、価格差の理由が透けて見え、納得のいく選択に近づけます。

 0120-962-165
0120-962-165