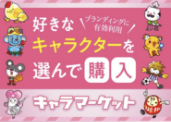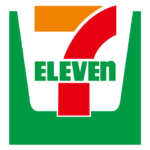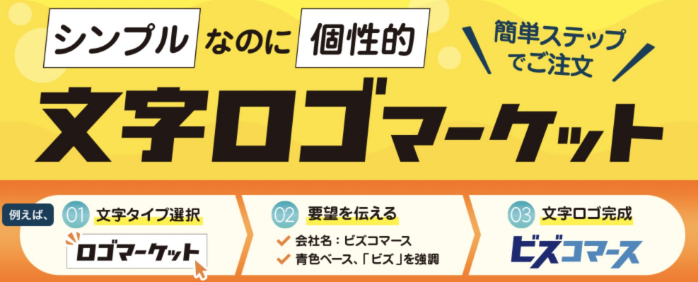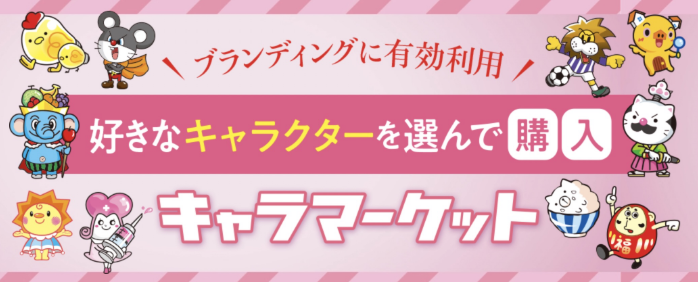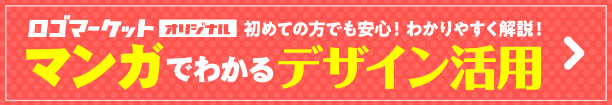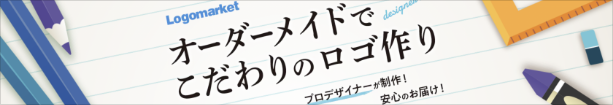Contents
結論:ロゴは“作った瞬間より、使われる瞬間”のほうが重要
AIロゴを作り、整え、展開してきたブランドは、ここで最終仕上げ。ブランドガイドライン(スタイルガイド)は、デザインを誰が触ってもブレなくなる“公式ルールブック”。
初心者でもプロのように見せられる完全テンプレにまとめました。これをそのままコピペして、あなたのブランドに置き換えて使ってください。
ブランド概要(Brand Overview)
ブランド名
○○(アプリ名/サービス名)
ブランドの目的
誰が、どんな課題を、どう解決するサービスなのか。
例:「家計管理をラクにするための、初心者向け家計簿アプリ」
ブランドの価値(Value)
例:シンプル、安心、親しみ、継続しやすい(※ロゴの方向性や配色と必ず整合性を取る)
ロゴガイド(Logo Guide)
ロゴの基本形
・メインロゴ(横長/縦長)
・アプリアイコン(正方形)
・シンボル単体(マークのみ)
用途別に3種類は必ず用意する。
- SNS → 正方形
- Web → 横長
- 印刷物 → 高解像度PNG or SVG
余白ルール(Clear Space)
ロゴの周囲にはロゴの1/3サイズ以上の余白を取る。
他の要素とくっつけない。
例:[□□□□ ロゴ □□□□]
サイズ最小値
視認性を保つため、以下を下回らないこと。
- Web:幅120px
- SNSアイコン:500×500
- アプリアイコン:1024×1024(正方形)
色のガイド(Color System)
AIロゴの色は、ブランド世界観の中核。
以下のように「メイン・サブ・アクセント」を必ず定義。
メインカラー
例:HEX:#37A6FF
用途:背景・CTAボタン・見出し
サブカラー
例:HEX:#FFFFFF
用途:本文・ロゴ内の白要素
アクセントカラー
例:HEX:#FFC861
用途:強調したい要素・リンクカラー
フォントガイド(Typography)
見出し(Heading)
フォント名:Montserrat / Bebas Neue
使用場所:H1〜H3、LPの強調箇所
太さ:Bold
本文(Body)
フォント名:Noto Sans JP / Lato
使用場所:記事・説明欄・CTA下部テキスト
太さ:Regular
文字間隔/行間
・文字間(Tracking):+1〜+4
・行間:140%前後
→ これだけでデザインがプロ品質に近づく
レイアウト・構図ルール(Layout & Composition)
ロゴ配置
・Web:左上
・SNS投稿:左上(固定)
・アプリ:中央 or 左上
角丸の統一
角丸があるロゴの場合:
・投稿テンプレ:角丸20〜30%
・バナー/OGP:角丸をロゴと合わせる
影の使い方
・影はNG(ロゴを濁らせる)
・必要な場合は 0px/0px/8px のごく薄い影のみ
使用例(Do & Don’t)
Do(正しい使用例)
- ロゴの周りに十分な余白
- SNS投稿は必ずブランドカラーで構成
- アプリ内UIのボタン色とロゴアクセントを揃える
- 画像・背景は同系色で統一
Don’t(禁止事項)
- ロゴの色変更
- ロゴの変形・ストレッチ
- 背景とロゴが同じ色で見えなくなる配置
- シャドウ・輪郭線の追加
- SNSごとに違う色やフォントを使うこと
SNS・アプリ・Webでの実用ルール
SNSアイコン
- 正方形版ロゴを使用(余白あり)
- 背景色=メインカラー or 白
- 小さくしても読めるか確認
投稿テンプレ(Canva)
推奨構成:
背景:メインカラー
左上:小さくロゴ
中央:タイトル(10〜14字)
下部:説明文2〜3行
アプリUI
- ホーム画面のボタン色=ロゴアクセントカラー
- アイコン角丸率=投稿画像と共通
- テキストはNoto Sans JP or Lato
Web(LP・ブログ)
- ファビコン:ロゴのシンボル単体
- OGP:ロゴ大+メインカラー背景
- CTAボタン:アクセントカラー
- 余白:上下80px+ロゴ比率に合わせて
テンプレート:ブランドガイドラインPDFの構成
CanvaでPDF化する場合、この目次が最適
- ブランド概要
- ロゴ使用ルール
- 色・フォント設定
- レイアウト(余白・角丸)
- SNS仕様(投稿テンプレ/アイコン)
- Web仕様(OGP/ファビコン)
- アプリUI仕様
- 禁止事項
- ダウンロード素材一覧
AI×人が作るブランド運用の未来
AIは:
- ロゴ案生成
- 配色提案
- 投稿テンプレの量産
- 写真素材の生成
人は:
- 世界観の決定
- 色や比率の判断
- 禁止事項の決定
- ブランドの方向性作り
この2つを統合すると、
「小さく始めて、大きく育つブランド」が作れる。
まとめ:ガイドラインは“ブランドの骨格”
AIロゴは、作って終わりではなく、
全ての媒体で“同じ物語”を伝えるための設計書が必要。
それがガイドライン。
今日からあなたのブランドは、
プロのように一貫性のある世界観を持つデザインに進化します。

 0120-962-165
0120-962-165