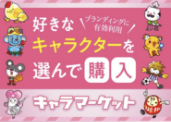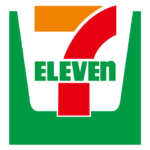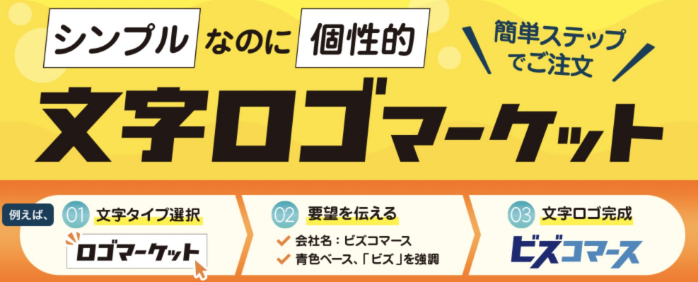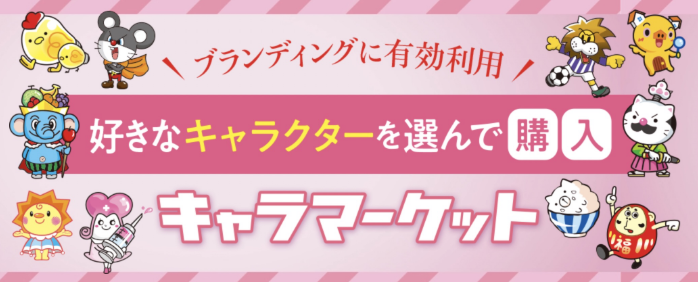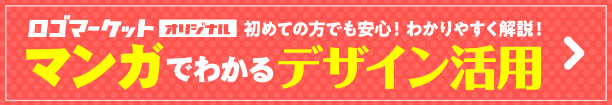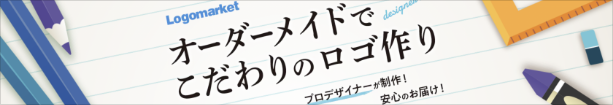AIで作ったロゴは、そのままだと著作権が発生しない場合がある一方、他人の著作権や商標を侵害するリスクは普通にある。鍵は、人がどこまで創作に関与したかと、商標の類否をきちんと避けること。学習段階、生成・利用段階、保護と登録の三つのレイヤーで整理し、段取りで守るのが最短ルートだ。
Contents
なぜAIロゴの著作権はグレーになりやすいのか
日本法の基本は、人の創作に著作権が発生するという考え方。AIが自律的に作っただけだと著作物性が認められない可能性があるが、出力を見ながら構図や線、余白、字間、色などを具体的に調整し、創作的寄与があれば、人が創作した著作物として保護され得る。長いプロンプトであっても、単なるアイデア列挙にとどまると弱い。選択や修正のプロセスに具体的な創作があるかどうかが判断軸になる。
学習(トレーニング)段階の整理
日本には情報解析のための例外があり、著作権者の許諾なく学習用に複製できる場面があると整理されている。ただし、権利者の利益を不当に害する態様や、海賊版由来の大量収集、特定作家の表現を狙い撃ちで再現するような運用は適用外になりうる。開発側も利用側も、出典と収集プロセスの透明性を意識しておく。
生成・利用段階の論点
出力を生む行為と、その出力を使う行為は別に評価される。ロゴの実務では、既存作との類似性と依拠性が主要な判断材料になる。たとえ学習段階が適法でも、最終成果物が既存作と十分に似ていれば侵害と評価される余地がある。逆に似ていなければ侵害にはならない。使い方次第で違法になる可能性がある点を常に意識する。
商標というもう一つの盾
著作権の有無にかかわらず、ロゴは商標として登録できる。識別力があり、先願と紛らなければ、AI関与でも登録自体は可能だ。つまり、AIロゴでも商標登録で独占権を確保できるし、他人の商標に近ければ侵害や拒絶の対象になる。出願前の類否調査は必須と捉える。
海外動向
米国の整理:人間の創作が鍵
米国著作権局は2025年1月にレポート第2部(著作物性)を公表し、生成AI出力の保護は人間の創作が具体的に読み取れる場合に限られるとあらためて示した。登録実務もこの考えに沿うため、申請時に「どこを人が作ったか」を説明できる記録が重要になる。
代表訴訟の一つであるAndersen v. Stability AIほかでは、2024年に多くの主張が整理され、CMI(著作権管理情報)関連など一部が棄却される一方、直接侵害等は係属を続けるなど、長期戦の様相。最終判断が業界ガイドラインになるまでには時間がかかる見込みだ。
参考サイト:united states copyright office,copyright alliance,McKool Smith,CourtListener
EU:AI法で透明性と著作権対応を制度化
EUはAI法を採択し、一般目的AI(GPAI)について、2025年8月2日から透明性・著作権関連の義務が順次適用。訓練データの要約公開など、権利行使を助ける枠組みが動き出した。モデル提供者の説明責任が強化され、ユーザー側の適法性評価や異議申立て対応がしやすくなる。
参考サイト:European Commission,reuters,Future of Life Institute
英国:Getty訴訟で争点を再編
英国・高等法院のGetty Images v. Stability AIでは、2025年6〜7月の審理の過程で、主要な著作権侵害クレームの取り下げが報じられ、二次的侵害や商標・パッシングオフ等に焦点が移った。係争は続いており、事案ごとの個別判断と自主ルールの整備が並走していく流れだ。
参考サイト:Pinsent Masons ,Shoosmiths ,Taylor Wessing
中国:人の関与があれば保護する方向
北京インターネット法院の2023年判決(Li v. Liu)などを皮切りに、ユーザーの知的投入が反映されたAI生成画像に著作権保護を認める動きが見られる。日本・米国の「人間性」要件と結論は近く、中国は人の関与の閾値を比較的広めに捉える傾向がうかがえる。
参考サイト:
ケースで学ぶ: 合法かつ安全に着地させる流れ
想定は新規カフェのシンボル+ロゴタイプ。
- 要件と言葉を先に固める。雰囲気、配色、用途、禁止事項を明記し、特定作家・特定ブランドの狙い撃ちを避ける。
- 幅広い方向で初期案を出す。似通った領域に偏らないよう、3方向×各3案を目安に。
- 選んだ案に人の創作を乗せる。線幅、角の処理、字間、余白、色の微調整を加え、修正ログを残す。
- 類否チェックを行う。既存作と商標の両面を確認し、危険なら即ピボット。
- 保護戦略を分ける。著作権は創作寄与の記録、商標は出願で権利化。利用条件は社内ポリシーと契約で整える。
利用規約とデータソースの見方
ツールごとに、出力のライセンス、学習への二次利用、アップロード素材の扱い、企業向けの保証範囲が違う。ビジネス利用なら、学習利用のオプトアウト可否、秘密保持、クレーム時の補償の三点は最低限チェックしておきたい。素材側ではフォントのロゴ化可否、写真素材の商用可否、二次配布の可否などを記録しておく。
よくある勘違い
AIが作ったら全部自由に使えるという誤解があるが、似ていれば侵害になる可能性はある。長い指示文があるだけで著作権が生じるわけでもない。学習は常に安全という考えも誤りで、収集源や目的次第では違法リスクがある。
実務フロー(初心者版)
要件整理 → 初期案の幅出し → 人の手で仕上げ(創作性の追加) → 類否と商標チェック → 商標出願 → 利用規約とライツ調整。
この順で進めると、著作権と商標の地雷を同時に避けやすい。
社内AIロゴ運用ポリシー(テンプレート)
目的: AIを用いたロゴ制作を合法・安全・再現性のあるフローに統一し、ブランドと権利を守る。
- 適用範囲
- 対象はロゴ、アイコン、ピクト、ブランド用画像。関係者は企画、デザイン、広報、法務、外部パートナー。
- 基本方針
- 幅広く出す → 狙い撃ち模倣を避ける → 人の創作で仕上げる。原本はベクターで管理し、履歴と決裁ログを保存。重要媒体はソフトプルーフか事前校正を原則とする。
- プロンプト方針
- ブランド要件と禁止事項を明記。特定作家名や既存ブランド名、完全再現を指示する文言は避ける。出力は白背景、ベクター想定、小サイズ視認性を明確にする。
- 素材と学習データ
- アップロード素材は使用許諾を確認し、秘密保持設定を見直す。学習への供出は可能な限りオプトアウト。
- 生成から採択まで
- 方向性出し、候補選定、創作的寄与の追加、ベクター整形、類否チェック、決裁の順に進め、各段階をログ化する。
- 権利チェック
- 創作寄与はスクショと文面で残す。商標は名称と図形で調査し、衝突の芽があれば別方向へ。フォントはロゴ化可・商用可を確認。
- 商標方針
- 屋号やサービス名と図形ロゴを対象に、公開前または同時期に主要区分で出願。改変や派生ロゴは再評価する。
- ログと保存
- プロンプト、生成画像、採否理由、修正前後、決裁、外部との授受を保存。期間はプロダクト存続プラス数年を目安。
- 事故時対応
- 申し立てを受領したら即時停止。法務と連携し、差し替え案を提示。再発防止としてプロンプト、チェック体制、外注管理を更新。
- 見直し
- 半期ごとにポリシーをレビューし、法令やツールの変更を反映する。
社内申請ワークフロー(ひな形)
目的: プロジェクト開始から公開までの意思決定と記録をスリムに一元化する。
- 企画申請
- 申請者は目的、用途、想定媒体、納期、禁止事項、参考資料を1ページで提出。テンプレに沿って作成し、デザイン責任者と法務へ同報。
- 設計承認
- デザイン責任者が要件の妥当性を確認し、足りない要素があれば差し戻す。法務は利用規約と素材権利の観点から承認。承認番号を発行。
- 生成フェーズ開始
- プロンプトの初版を登録し、生成ログを自動保存。初期案は3方向×各3案を目安に幅を確保。特定作家やブランドの狙い撃ちは禁止。
- 創作寄与の追加
- 選定案に対し、線幅、角、字間、余白、配色の調整を実施。修正点と判断理由を記録。
- 類否チェック
- 名称と図形で簡易スコアリングを実施。合計スコアが要注意以上なら、別方向案へ即ピボット。必要に応じて専門家にエスカレーション。
- 校正と最終決定
- 必要に応じてソフトプルーフか簡易校正を実施。結果をもとに最終調整。デザイン責任者と法務が共同で承認。
- 商標対応
- 出願方針を決定し、出願作業に着手。出願済みの証跡をプロジェクトに添付。
- 納品と展開
- AI、PDF、SVG、PNGを所定フォルダ構成で納品。運用先のガイドラインに反映。
- 事後レビュー
- 公開後に軽微な問題があれば是正。重大な申し立てがあれば運用停止、代替案の提示、再発防止策の更新を行う。
商標の簡易類否チェック表(ロゴ用)
使い方は五分で終わる一次スクリーニングを想定。名称と図形を分け、外観、称呼、観念、指定商品・役務、先使用の五観点を各0から1で評価し、合計2以上を要注意とする。
| 観点 | チェック内容 | 目安(OKライン) | 要注意例 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 外観(図形) | 形・輪郭・構図・線の比率が重なるか | 全体印象が別物 | シンボルの骨格がほぼ同じ | 反転/傾き程度は同視されやすい |
| 称呼(呼び) | 読みが近いか(ハ・バ等の濁点含む) | 明確に異なる | 「ホップライト」と「ホプライト」 | 片仮名/英字の差は弱い |
| 観念(意味) | 連想・意味がかぶるか | 無関係 | 同じ動物・同じ象徴 | 図形+名前の組合せで近づく |
| 指定商品・役務 | 同じ/近い分類か | 遠い | 同一/近接区分 | 同業なら厳しめに判定 |
| 先使用実績 | 相手に実使用・知名度があるか | 低い | 高い | ローカルでも要注意 |
判断のコツ
- 全体観察が基本。細部ではなく第一印象で近いなら危険。
- 図形が遠くても、呼びが同じならNGになりがち。
- ロゴタイプは書体を変えても称呼が同じなら要注意。
- 迷ったら名称を替える方が速いことが多い。
記録テンプレ(コピペOK)
案件名:_____
日付:_____
候補ロゴ名:_____(読み:__)
比較対象(名称):__/__/__
比較対象(図形):__/__/__
判定:OK/要注意/NG
理由(外観/称呼/観念/区分/先使用):________
次アクション:別方向案へ/名称差替え/専門家相談/出願準備
担当:_____
制作指示書(社外共有用)
依頼や見積りの前に、そのまま貼って使える書式。
ブランド:________/一言説明:________
目標印象:ミニマル/親しみ/高級感(いずれか複数)
配色:メイン____(RGB/HEX)、アクセント____
禁止:既存ブランド連想/作家名の狙い撃ち/写真要素
生成要件:白背景/ベクター想定/小サイズ視認性
提出:3方向×各3案/モック不要
仕上げ:線幅・角R・字間・余白の具体調整を必須
権利:フォント商用可・ロゴ化可/出力の二次利用オプトアウト
調査:名称・図形とも一次類否チェック実施
成果物:AI/PDF/SVG(原本)+PNG(1024/512px)
校正:必要に応じソフトプルーフ/簡易校正1回
記録:プロンプト・修正・決裁ログを納品
外注契約の条項テンプレ(AI利用あり)
注意: 実際の契約は専門家確認を推奨。このテンプレはたたき台。
第1条 定義
生成AIとは、指示文等に基づき画像を自動生成するシステムをいう。成果物とは、本契約に基づき制作されるロゴ等のデザインをいう。
第2条 利用範囲
受託者は、成果物の制作に生成AIを利用できる。ただし、特定作家や既存ブランドの表現を狙い撃ちする指示は禁止する。
第3条 知的財産権の帰属
成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条を含む)は、甲への納品完了時に甲に移転する。移転に必要な同意、承諾、第三者の権利処理は乙の責任で行う。
第4条 素材等の権利保証
乙は、使用するフォント、画像、テクスチャ等について、ロゴ化や商用利用が可能であることを保証し、第三者の権利侵害がないよう配慮する。
第5条 生成AI出力の扱い
乙は、生成AIの利用規約を確認し、成果物の商用利用に支障がないことを保証する。学習への二次利用やデータ提供のオプトアウト設定が可能な場合は、原則としてオプトアウトを選択する。
第6条 類否調査
乙は、成果物の採択前に、名称及び図形の簡易類否チェックを実施し、結果を甲に報告する。必要に応じて専門家による調査を提案する。
第7条 秘密情報
甲から提供を受けた情報は秘密情報とし、目的外に使用してはならない。生成AIツールに入力する情報については、当該ツールの利用規約に照らし、安全性を確認する。
第8条 保証及び補償
乙は、成果物が第三者の権利を侵害しないことを保証し、侵害の申し立てがあった場合は自己の費用と責任で解決する。必要に応じて差し替え案の提供等、甲と協議のうえ適切に対応する。
第9条 再委託
再委託を行う場合は事前に書面承諾を得る。再委託先にも本契約と同等の義務を課す。
第10条 成果物とデータの引渡し
乙は、AI、PDF、SVG、PNG等のデータを所定形式で納品し、生成過程の記録(主要プロンプト、修正履歴、採否理由)を併せて提出する。
第11条 本条項の見直し
法令や主要ツールの利用規約の変更に応じて、当事者は本条項の見直しを協議する。
FAQ
Q1: AIロゴは著作権で守れるのか
A: 人の創作的寄与が十分なら、AIを道具として使った人の著作物として保護され得る。寄与が弱ければ保護されない可能性がある。
Q2: 学習に他人の作品が入っていたら違法か
A: 情報解析の例外があるが、権利者の利益を不当に害する態様や海賊版源の収集はリスクが高い。
Q3: 商標登録はできるか
A: 識別力があり、先願と紛れなければ、AI関与でも登録可能。出願前に類否調査を行う。
Q4: 海外の訴訟は日本実務にどう影響するか
A: 現時点では確定的な国際ルールは少ない。日本の実務は段取りを整え、必要な箇所だけウォッチするのが現実的。
Q5: 安全に運用する最低限のコツは
A: 狙い撃ち模倣を避ける、創作寄与を残す、商標で権利化、規約とデータ源を確認。この四点で大半の事故は避けられる。
まとめ
AI時代のロゴ制作は、著作権と商標を分けて考えると整理が早い。まず幅広く出し、特定作家や特定ブランドの表現を狙わない。次に、人の目と手で線や余白、文字組、色を具体的に整え、創作的寄与を積み重ねる。ここまで来たら、既存作との類否、先行商標との衝突を確認し、商標で権利を固める。学習と利用の合法性は段階ごとに論点が違うが、非享受目的のラインを守り、似ている状態を避け、出所の怪しい素材を踏まない。この三点を外さなければ大事故は起きにくい。
海外の係争は進行中で、結論は動く可能性がある。だからこそ、今できる再現性の高い段取りで進める。ログを残し、社内ポリシーと申請フローを整え、外注契約で保証と補償のリスク配分を明確にする。センスではなく仕組みで守り切る。AIのスピードを味方に、あなたのロゴを安心して使える資産へ育てていこう。
主な公開情報(参考リンクだけまとめ)
小野デザイン|AIによるロゴデザイン、著作権と商標権にご注意
https://www.onodesign.co.jp/designessay/2023/04/27/ai%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%80%81%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9%E3%81%AB%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%84%8F/
メタバース総研|生成AIと著作権
https://metaversesouken.com/ai/generative_ai/image-copyright-2/
Neural Opt|AI×著作権の裁判・事例まとめ
https://neural-opt.com/ai-copyright-cases/
BAYS CROSS|生成AIと著作権の基礎
https://www.baycross.jp/column/production/ai-copyright
NTTコム|AI×著作権の基礎
https://www.ntt.com/bizon/copyright_ai.html
SHIFT AI|生成AIの著作権問題
https://shift-ai.co.jp/blog/5514/
企業法務ナビ|AIと著作権の論点
https://houmu-pro.com/property/297/
米国著作権局(USCO)AIレポート第2部(著作物性・2025年1月)
https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf
USCO「AIと著作権」特設ページ
https://www.copyright.gov/ai/
EUデジタル戦略|AI法(適用タイムライン)
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
EUニュース|GPAIの透明性義務適用開始(2025年8月2日)
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-rules-general-purpose-ai-models-start-apply-bringing-more-transparency-safety-and-accountability
Getty v. Stability AI(英国)関連解説
https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/getty-images-stability-ai-copyright-claims-dropped
https://www.taylorwessing.com/en/insights-and-events/insights/2025/07/getty-v-stability
https://apnews.com/article/7208c729fb10c1f133cb49da2065d72a
北京インターネット法院判決(AI画像の保護)解説
https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/
https://natlawreview.com/article/beijing-internet-court-recognizes-copyright-ai-generated-images
https://globallitigationnews.bakermckenzie.com/2024/05/08/china-a-landmark-court-ruling-on-copyright-protection-for-ai-generated-works/
※法的助言ではなく一般的情報です。重要な案件は必ず専門家に相談してください。

 0120-962-165
0120-962-165