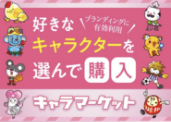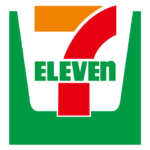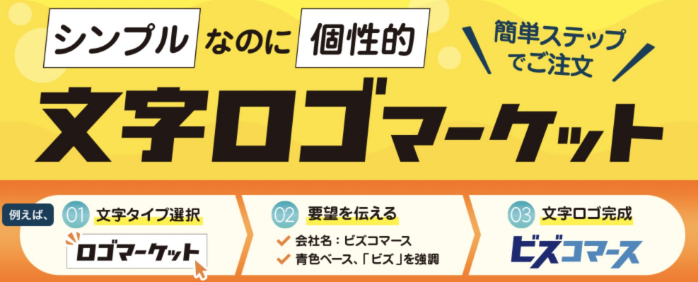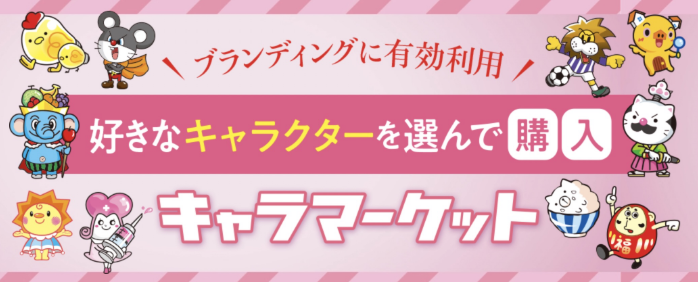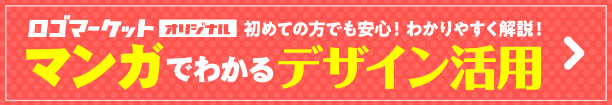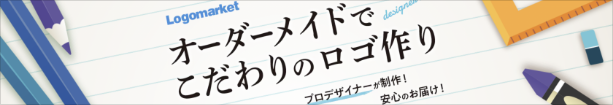AIでロゴを作るときの出来不出来は、色彩・フォント・マーク比率(レイアウト)の三本柱を数値と言葉で先に決めるかどうかでほぼ決まる。さらに、プロンプトの骨格を固定し、出力をスマホ実寸で検証するだけで、初心者でも“当たり”の割合は大きく上がる。ここでは、IllustratorやCanva未経験でも迷わないように、各要素を実務目線で深掘りし、すぐ流用できるプロンプトと評価ルーブリック、FAQまでひとまとめにする。
Contents
色彩:三色で設計し、明暗差を固定する
色は印象の7割を決めるが、増やすほど運用が不安定になる。最初はメイン1色、サブ2色、ニュートラル(黒/白/グレー)の三色構成で着手するのが安全だ。ポイントは明度差を固定すること。メインとサブが同じ明るさだと、SNSアイコンなど小サイズで濁って見える。まずはメインのHEXを決め、サブ2色はメインの明るい側と暗い側に配置する。背景が明るい場面と暗い場面の両方を想定し、反転版も同時に用意しておくと、媒体が変わっても破綻しにくい。
色を決めたら、スマホ実寸で確認する。PCの拡大表示は良く見えても、実寸では埋もれがちだ。ビビッドな色で潰れるときは彩度を落とすより、明暗コントラストを強める方が視認性は上がる。黒は用途別に二枚用意すると管理が楽になる。テキスト用の落ち着いた黒と、見出しや大きな面を締める深めの黒だ。
生成時の書き方は、役割付与の一文に続けて、配色を具体値で指示し、反転版と単色運用の両立を求めるのがコツ。例として、メイン#2F3E46、サブ#A3B18Aと#D9E4DD、反転版も出力、単色でも読める、といった具合に短く区切ると通りやすい。
フォント:ジャンル→字間→角の順で整える
フォントは雰囲気と可読性と差別化の綱引きだ。まずジャンルを決める。サンセリフはモダン、セリフは格調、スラブは力強さ、丸ゴは親しみといった“声色”を先に選ぶ。次に字間。AIの初期出力は詰まり気味なので、スマホ実寸で読めるところまでトラッキングを広げ、必要に応じて個別カーニングを入れる。最後に角の処理。直線的なキリッとした印象なら角を立て、やわらかさを狙うなら角をほんの少し丸める。角丸はやり過ぎると幼く見えるので加減が大事だ。
フォント指示の書き方は、ジャンル、ウェイト、字間の傾向、角処理を一息で指定し、既存ブランド連想は避けると添える。たとえば、細身サンセリフ、字間やや広め、角はわずかに丸める、小サイズ可読、既存連想禁止、といった短文が効く。
マーク比率とレイアウト:ロックアップを数値で決め打ち
どれだけ良いマークでも、ロゴタイプとの関係が曖昧だと安定しない。先にロックアップ(配置)と比率を決め打ちすると出力の迷走が止まる。基本の型は三つ。横組み(マーク左・文字右)は汎用性が高い。スタック(縦積み)は正方形に強く、バッジ(円や盾の中)はイベントやグッズに映えるが文字が小さくなりやすい。
はじめの数値基準はこう置く。横組みならマーク:文字高さ=1.2:1。外周余白はロゴタイプのxハイト相当。最小サイズは幅24〜28px相当でも識別できること。白抜きの細線は潰れやすいので構造から避ける。これらをプロンプトに常設すると、方向性が安定する。
形状と線:情報を削る勇気が“精度”をつくる
AIは細部を盛り込みがちだが、ロゴは逆で削るほど強くなる。内部線は縮小しても一本として残る太さを最低ラインにする。角Rは雰囲気を整える万能ツールだが、丸め過ぎはキャラクター化の原因。円や斜線が揃って見えないときは、オーバーシュート(目視で揃うように少しはみ出す)を意識すると、パス化後に安定感が出る。出力後はVectorizerやInkscapeでベクター化し、線幅と角Rを微調整する流れにしておくと良い。
出力と検証:四面チェックで一発合格に寄せる
検証はまとめてやるのが時短のコツ。明るい背景での可読、暗い背景の反転可読、スマホ実寸の縮小表示、SNSアイコン・サイトヘッダー・名刺の簡易モック。四面で違和感が出るなら、多くは字間かコントラストの問題だ。ここを先に直せば、ほとんどの不満は消える。評価は感覚ではなく基準で行う。次章のルーブリックをそのまま使うと、合議が早い。
評価ルーブリック(会議で揉めないための1枚)
視認性、一貫性、再現性、個性の四観点を5点満点で採点し、平均4点以上で合格とする。
視認性:明・暗どちらでも小サイズで判読できる
一貫性:マークとタイプのトーン、線幅、角の処理が揃っている
再現性:単色運用と反転運用でも崩れない
個性:過度に複雑でなく、他と混同しにくい要素がある
平均が3点台なら、どこを直せば4になるかを一文で言い切る。例として、字間+8%、マークの線幅+0.2pt、メインとサブの明度差+10、のように数値を添えると再生成が速い。
プロンプトの構造化:役割→条件→形式の三層
安定する書き方は、役割付与、制約と数値、出力形式の三段構成だ。下の雛形をそのまま使ってよい。
目的行:あなたはロゴデザイナー。初心者でも運用しやすい視認性重視のロゴを提案して。
条件行1:ロックアップは横組み固定。マーク:文字高さ=1.2:1。外周余白=文字のxハイト。白抜き細線は禁止。
条件行2:ロゴタイプは細身サンセリフ。字間やや広め。角はわずかに丸める。
条件行3:配色はメイン1色(#XXXXXX)とサブ2色(#YYYYYY/#ZZZZZZ)。反転版も同時出力。単色運用でも破綻しない。
禁止行:既存ブランド連想と作家名の指定は禁止。白背景で提示。モック不要。
形式行:見出し、説明、色コード、SVG的な構造説明、縮小時の配慮点を箇条書きで。
ケーススタディ:カフェの新規ロゴを狙って当てる
条件は親しみ、清潔感、ミニマル。色は落ち着いた青緑をメイン、ミントとクールグレーをサブにして明暗差を確保。ロックアップは横組み、比率1.2:1で固定。マークはコーヒー豆や湯気の要素を抽象化し、三要素以内に削る。ロゴタイプは細身サンセリフで、字間をスマホ実寸で読めるところまで広げる。暗い背景へは反転版で対応し、沈むならメインの明度をわずかに上げるか、サブを背景側に回す。出力は三方向×各三案で幅を確保し、まず数値条件に合っているかだけで選別。合格案にだけ角R、線幅、コントラストの微調整を入れ、ベクター化後に最小サイズテストを行う。白抜きの細線が残るなら構造自体を見直し、線の有り無しで情報を削る。
ノンデザイナー向け最短ワークフロー
- 目的と言葉を一段で書く(雰囲気、用途、禁止事項)
- 三色設計とロックアップの数値を決める(1.2:1、xハイト余白など)
- 三層プロンプトで三方向×各三案を生成
- 数値合致だけで一次選抜、合格案だけ字間・角R・線幅を詰める
- 四面チェック(明・暗・縮小・模擬)を一度に実施
- 色、最小サイズ、余白、反転版の条件をメモにして運用へ
よくある質問(FAQ)
Q1. 生成のたびに仕上がりがバラバラになる
A. 比率、外周余白、字間の基準値をプロンプトに常設していない可能性が高い。ロックアップ固定、マーク:文字高さ=1.2:1、xハイト余白、字間はやや広め、といった定型を必ず入れる。
Q2. 画面だと綺麗なのに、アイコンにするとにごる
A. 明度差が不足している。メインとサブの明るさを意図的に離し、単色運用で読めるか先に確認する。彩度よりコントラストを優先する。
Q3. フォントを替えたら雰囲気が崩れた
A. 角の作法と字間が変わったせい。同じ系統内で差し替え、角Rと字間を元の設計値に戻してから微調整する。
Q4. マークが複雑になってしまう
A. 形の役割を三つまでに制限する(大形・中形・小形)。余分な切れ込みや装飾は捨て、縮小時に一本の線として残る太さを最低ラインにする。
Q5. 暗い背景で沈む
A. 反転版を用意し、メインの明度を一段上げるか、背景側にサブを回してコントラストを確保する。
Q6. どこで完成と判断すればいいか
A. スマホ実寸で幅24〜28px相当まで縮小し、一瞬で読めたら止める。読みにくい場合は字間とコントラストから直す。
Q7. 商用で使う上の注意はあるか
A. 既存ブランド連想の禁止をプロンプトに明記し、生成後は簡易の類似チェックを行う。フォントは商用・ロゴ化可否を必ず確認する。
まとめ
AIロゴの精度は、設計の言語化で作れる。色は三色設計で明暗差を確保、フォントはジャンル→字間→角の順で整え、ロックアップは比率と余白を数値で決め打ちする。出力は四面チェックで一度に判断し、修正は字間とコントラストから。プロンプトは役割→条件→形式の三層に分け、毎回同じ骨格を使い回す。道具の巧拙より、この段取りが効く。今日のプロンプトに比率、余白、字間の一行を足してみよう。出てくる案の落ち着きが、すぐに変わるはずだ。
参考(本文設計に反映した主な公開情報)
ChatGPTでロゴを作るプロンプト例とコツ|SHIFT AI for Biz
https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/chatgpt-logo-prompt/
note|AIでブランドロゴを生み出す考え方
https://note.com/tasty_dunlin998/n/ne7e8c68ffa8f
非デザイナーがAIでロゴを生成する方法|Handmade Marketing
https://handmade-marketing.net/generate-logo-by-ai
ChatGPTでロゴ作成と商用利用の注意点|Hakky Handbook
https://book.st-hakky.com/business/chatgpt-logo-commercial-use-guidelines
note|AIロゴ制作の実践メモ
https://note.com/hiro_seki/n/n27f36dc646f9
生成AIプロンプトの作り方|Cloud CIRCUS
https://ai.cloudcircus.jp/media/column/gen-ai-prompt-tips
AI×デザインの実務コラム|momocri
https://momocri.jp/column/column-653/
Midjourneyとベクター化の流れ|Cosmoway
https://f4.cosmoway.net/midjourney_logo/
ロゴマークとロゴタイプの基礎知識|RAD FLAG GALLERY
https://www.radflaggallery-design.com/

 0120-962-165
0120-962-165