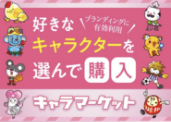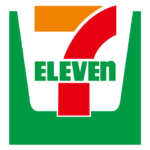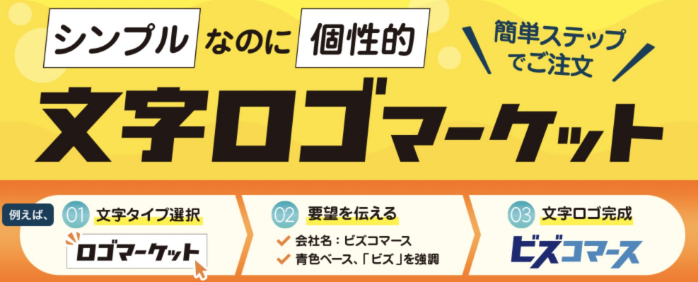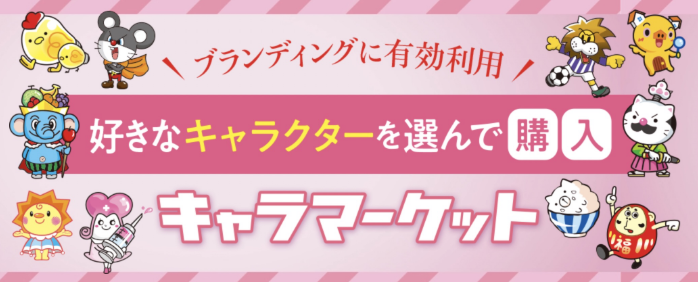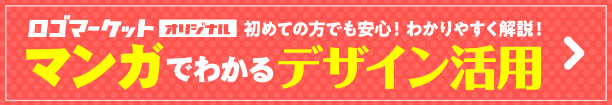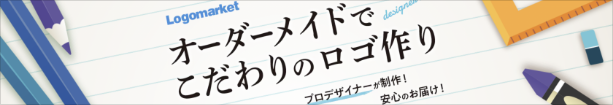1898年に設立された日本楽器製造株式会社が、ヤマハの前身です。設立の翌年である1898年に、社章として「音叉」が、商標として「音叉をくわえた鳳凰図」を制定し、以降多様な変化を遂げながら現在のヤマハロゴになりました。
今回はそんなヤマハの「ロゴの歴史」を参考に、ロゴマークの変遷を追いかけます。ロゴマーク作成のヒントが見つかるはずです。
※本記事では、比較・検討のため著作権に規定された範囲内で画像を引用しております。そのため、引用画像の権利は著作者に帰属しています。
Contents
ヤマハのシンボル音叉マーク
トランペット奏者のジョン・ショア(1662~1751)が発明した音叉は、調律などに使用される道具です。U字型の棒の中央に柄をつけ叩いて音を出すことで、振動数を調律の基準にしています。
ヤマハのシンボルには、3本の音叉が組み合わされたマークが用いられています。3本の音叉は、「技術」「製造」「販売」の3部門をイメージしており、強い協力体制とヤマハのたくましい生命力を表しています。この3本の音叉は他にも、音楽の基本「メロディー」「ハーモニー」「リズム」の調和という意味もあるとか。3本の音叉には、色んな思いが込められているのです。
1898年の音叉マーク
![[ 画像 ] 音叉をくわえた鳳凰図](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1898_01.gif)
1898年に、商標として制定された「音叉をくわえた鳳凰図」が音叉マークの始まりです。最高級品のオルガンに使用されたものとされており、常に世界水準を目指した創業者山葉寅楠の想いが込められています。ヤマハの名は、創業者の名字に由来しています。
ヤマハの音叉マークというと、3本が交わっているイメージがありますが、初期は鳳凰が音叉を咥えていたのは驚きですね。鳳凰は伝説の鳥であり、世界水準や最高級品というイメージにもピッタリです。
それではヤマハの音叉マークの歴史を、いくつかのロゴと一緒にたどってみましょう。
1916年に商標登録された3つの音叉マーク
1916年には3つの音叉マークが商標登録出願されました。
![[ 画像 ] 音叉マーク単独での図案](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1916_01.gif)
ヤマハのシンボルである音叉マーク。
![[ 画像 ] オルガン用音叉マーク](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1916_02.gif)
オルガン用の音叉マーク。
![[ 画像 ] ピアノ用音叉マーク](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1916_03.gif)
ピアノ用の音叉マーク。
いずれのロゴにも3本の音叉マークが用いられています。
1927年と1934年の音叉マーク
![[ 画像 ] 音叉マーク&山葉ベニア](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1927_01.gif)
「音叉マーク&山葉ベニア」が商標登録出願されました。
![[ 画像 ] 新聞や広告、カタログなどに広く使用](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1934_01.gif)
1934年に作られたこちらのロゴは、ピアノに社名そして音叉マークを組み合わせています。新聞や広告そしてカタログなどに幅広く使用されました。
1967年の音叉マーク
![[ 画像 ] ロゴ統一。現在の特殊形は、「裏図形」として制定](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1967_01.gif)
統一されたロゴです。現在の音叉マークはこのマークの「裏図形」になっています。この後いくつかのリニューアルを経ました。
2016年の音叉マーク
![[ 画像 ] 現在の音叉マークに統一](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_2016_01.gif)
特殊形の制定などを経て、2016年現在の音叉マークに統一されました、線がより太くなりハッキリとしています。
ヤマハのロゴマーク
シンボルである音叉マーク同様、ロゴマークもリニューアルを実施しています。ここでも主要なものを中心にみていきましょう。
▼1967年のロゴマーク
![[ 画像 ] ヤマハロゴを制定](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1967_02.gif)
音叉マークに社名を組み合わせたヤマハロゴを設定しました。裏図形として、現在のヤマハロゴに近いロゴも併用されていました。
ヤマハは設立当初の「音叉をくわえた鳳凰図」に込めた想いからもわかるように、早い段階から世界水準を意識しており、1958年にはメキシコに最初の海外法人である「ヤマハ・デ・メヒコ」を設立しています。そのため、社名も英語表記が使用されています。
1987年のロゴマーク
![[ 画像 ] 創業100年を機に「ヤマハ株式会社」に社名変更](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_1987_01.gif)
創業100年を迎えた際に、「ヤマハ株式会社」に社名を変更しました。この時ロゴからシンボルである音叉マークを外し、社名の「YAMAHA」を強調したロゴが作成されました。
2016年のロゴマーク
![[ 画像 ] 現在のヤマハロゴに統一](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/thum_2016_02.gif)
1998年のリニューアルで音叉マークが復活し、2016年には現在のヤマハロゴに統一されました。
番外編:ヤマハ発動機のロゴマーク
![[ 画像 ] ヤマハ発動機株式会社ロゴ](https://www.yamaha.com/ja/about/history/logo/images/logo_yamaha_motor.gif)
1955年に、オートバイ部門が分離しヤマハ発動機株式会社になりました。そのためヤマハとヤマハ発動機は、類似したロゴを用いています。
ヤマハ発動機のロゴは赤色をベースにしており、音叉の先が円い枠にくっついています。さらに、YAMAHAのMの音字の中央部分が下についており、各文字が左右対称になっているのも特徴のひとつです。良くみてみると、ヤマハのロゴは、YAMAHAの文字が左右非対称になっているのに気付くことができます。
音叉マークや「YAMAHA」という社名など、ベースは変わりませんが、色遣いやちょっとしたデザインの工夫で違うロゴに仕上がっているのは面白いですね。グループ会社では関係性をアピールするため、に同じロゴをベースに一部アレンジを加えることがありますが、こうした細かいデザインの違いにまで拘り作りこんでいることで、グループの姿勢を感じることができます。
おわりに
「ロゴの歴史に見る変化~ヤマハ編~」をご紹介しました。創業130年を超すヤマハのロゴマークには、設立当初からシンボルとして音叉が使用されてきました。
長い年月をかけて国内だけではなく世界で活躍するブランドに育ったヤマハ。ロゴ戦略を参考にすることで、長く愛され続けるヒントが見つかるかもしれません。他にもご紹介できなかったロゴがありますので、ぜひそちらにも触れてみてください。

 0120-962-165
0120-962-165